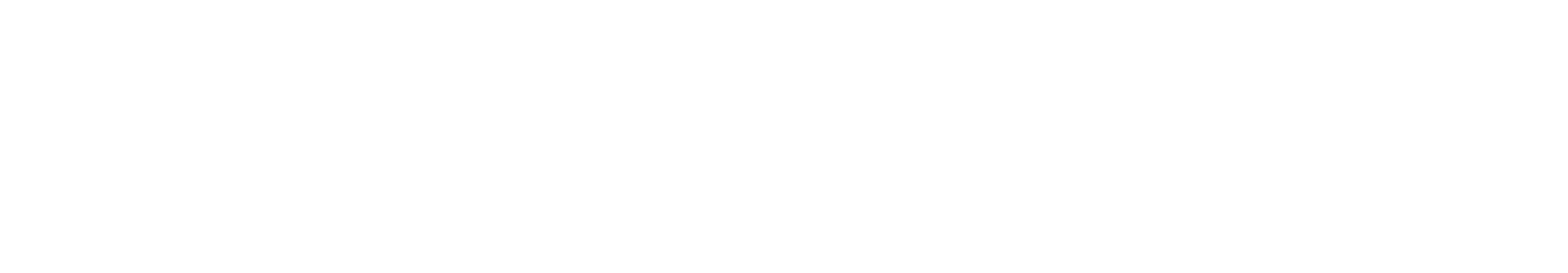忍者になりたい方へ
武神館は9流派が統合されています。その中には忍術も伝わっています。ただ、アニメや映画で見かけるようなアクロバティックなことは稽古していません。そういう稽古を求める方は、別の団体や教室の方がよろしいかと思います。
武神館が稽古しているのは本当の意味での忍術、護身術です。実際の危険な場面では、開始の合図もありませんし不意打ちかもしれません。1対1とも限らず敵は複数かもしれませんし、武器を持っているかもしれません。急所を狙ってはいけないというルールもありませんし、明るいところ、足場が良いところとも限りません。そういった様々な場面に臨機応変に対応し「生き延びる」ための技術を伝えています。そういう実際に使われていたであろう、古えの忍術を学びたい人には武神館の武道が合っているかもしれません。
さて、武神館が継承する9つの流派には、沢山の古武器が伝わっています。なかには現代のさまざまなスポーツ武道の源流のものもあります。これらの古武器や忍具の稽古は、古の人々の知恵の宝庫に触れる機会でもあります。武神館の稽古では、通常の武器の型稽古のほかに、自由な発想のもとに、相手が考えもつかないような武器の使い方をして、形勢を有利にする方法も学んでいきます。
・・・・忍者は忍具を自由に使う。ただひとつの目的にだけ役立たせるようには使わない。忍者は忍具を固定して考えない。(『戦国忍法図鑑』初見良昭著より抜粋)
危険な場面に遭遇するケースでは武器を持ち合わせていることが少なく、むしろ何も武器を持っていないことのほうが圧倒的に多いものです。
そういうシチュエーションに置かれた場合、周囲にあるなんらかの物を急遽武器として使うことで、その場を生きて逃れる確立を高めることができます。武神館には沢山の武器が伝わっているため、周囲の日用品であっても、どれかの武器となんらかの共通した形や質を持っていることが多いです。
追い込まれたとき、似たものを武器として使ったことがある経験から、咄嗟に周囲にある日用品を武器に見たてて対応できるので、有時にはとても役立つ護身となるでしょう。
武神館では、法律の制約もあり、現在は火薬を扱ったものなど一部の古武器の稽古は通常行っておりません。その場合は「こういうのも伝わっている」という知識のみの教授です。
また、ここに紹介するのは武神館に伝わっている古武器の一部であって、すべてではないことを、あらかじめご了承ください。また、道場で毎回すべてを稽古することはできません。人数や参加者の様子を見て師範がその日稽古する武器を決めています。
■武器
忍び装束
六具
忍者刀
鎖鎌
距跋渉毛(きょけつしょげ)
忍び槍
槍
眉尖刀
薙刀
旋盤手裏剣・つぶて・棒手裏剣
六尺棒
杖
半棒
六尺仕込み杖
鎖分銅
足砕・撒きビシ・伊賀玉
印籠
笠灯
手甲足甲
忍いかり
忍辱(にんにく)鎧
投げ鉄砲
鉄扇
苦無(くない)
しころ
十手
猫手
角手(角指)
目潰し
忍び矢・弓
吹き矢
忍び縄(梯子)
閉器
水器
抱え大筒(袖筒)
隠し武器(脇差短筒)
鉄拳
毒水鉄砲
くるみ
四つ竹
投網
箱船
忍術の流派においては、身体の治療の知識に長けていて、それらも伝わっています。詳細はここでは省きますが、希望者には少しずつお伝えすることもあります。
2014年、東京武道館で武神館の演武が行われました。武器紹介ともなっています。
当道場も、六尺仕込み杖の場面で参加しています。(6:15あたりから)