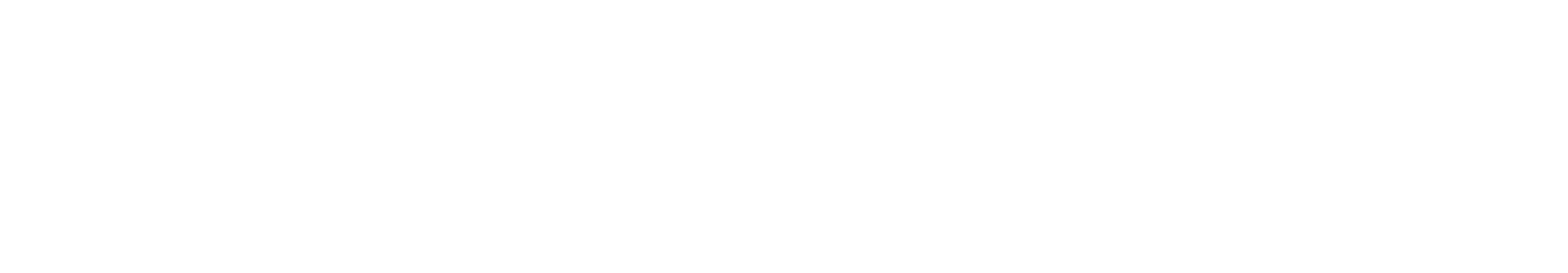手塚道場について 師範紹介
 ●指導者
手塚航(てづかわたる)大師範
●指導者
手塚航(てづかわたる)大師範
読売カルチャー講師として、7年間戸隠流忍法の講座をご担当していました。また、手塚道場も17年目を迎えています。武神館本部でも毎週火曜日に指導をしています。
後進の育成にも熱心で、2014年から大森カルチャー講座の講師は、手塚道場で修業を積んで師範資格を得た門下生に後を譲りました。強いお弟子さんを沢山輩出するのが夢といつも言っています。本部には海外からわざわざ日本に習いに来ている外国人も多く、本部での稽古を動画にしてくださった方もいますのでご紹介いたします。↓
手塚先生は、道場を構えた後も、週2回以上本部稽古に参加し、初見先生から教えを受けて技術を磨いてきました。常に自分の技術の向上をはかり、道場の誰よりも努力をし続け、その得たものを惜しみなく弟子に伝えようと努力してくれているのがわかります。また、カルチャー講師のご経験が長かったこともあり、教え方が明確で理路整然としており、教わるほうとしては大変わかりやすく質問しやすいです。
先生は柔道整復師として整骨院を経営しています。身体の仕組みの専門家として治療にあたっていて、門下生の健康相談にも的確に答えてくれる心強い面もあります。(HP管理人は長年の坐骨神経症体質とお別れできました。) 
先生は、15段、大師範位(武神館最高位)を取得後も、武風一貫し自身の研鑽と弟子の育成に励んでいるとのことで、宗家より賞とメダルを授与されました。どなたに対しても同じように丁寧な態度で接する人です。その門下に集まる人も、下は10代から70代までと幅広い年齢層ですが、先生と同様に紳士的な弟子が多いように思います。
支部の位置づけ
 千葉県野田市には、武神館の本部道場があります。こちらでは、武神館の創始者である初見宗家が師範クラスの実力を持つ門下生にたいして稽古を行っていました。最近、テレビで外国人が毎週100人近く集まるスポットとして本部道場が取り上げられるようになりましたが、あの様子は特別な光景ではありません。宗家の稽古は、もう30年以上、毎回あのような状態で、大勢の門下生が海外からわざわざ宗家の教えを受けるために来日していました。
千葉県野田市には、武神館の本部道場があります。こちらでは、武神館の創始者である初見宗家が師範クラスの実力を持つ門下生にたいして稽古を行っていました。最近、テレビで外国人が毎週100人近く集まるスポットとして本部道場が取り上げられるようになりましたが、あの様子は特別な光景ではありません。宗家の稽古は、もう30年以上、毎回あのような状態で、大勢の門下生が海外からわざわざ宗家の教えを受けるために来日していました。
(写真は宗家に指導をいただく手塚先生)
現在は跡を継いだ宗家の方々ならびに大師範の先生方が本部で教えていらっしゃいます。手塚師範も毎週火曜日夜に本部で教えています。
武神館においては、基本的に入門希望者は支部道場にまずは入門します。そして支部道場で研鑽を積み、上達した後、道場長の許可の下で本部の稽古に参加することも可能、という流れです。
さて、その支部道場についてですが、武神館の支部道場においては特に決まった教授課程などはなく、支部道場によって、その稽古方法・内容・昇段の基準が全く異なります。
また、原則、他道場への出稽古や移籍などは所属道場長同士の話し合いのもとで行われるのが慣例です。したがって、一度ある支部道場の門下生となりますと、たとえばスポーツクラブチェーンの会員制度のように、今日は自宅近くのジムに通い、明日は同じスポーツクラブの会社近くの違う店舗に通う、というように、複数の道場に平行して通うことは基本的にはできません(仕事の休日の理由、出張、転勤など例外はあります)。一人の師範のもとで一貫して稽古を行ったほうが上達が早いというのも、その理由です。
当道場においては、師範の手塚先生は、道場を開くときに宗家から「まず5段までは型稽古をしっかりやらせなさい。」と何度も言われたそうです。そのため、手塚先生は型稽古を中心に受身や武器、体術などの武神館の基礎を、初心者にもわかりやすいように、繰り返し懇切丁寧に教えています。
手塚道場は先生が道場を開いて17年目ですが、当道場には10人の士道師資格取得者(武神館における5段取得者。師範資格。)の門下生が所属し、資格取得後も今もなお手塚道場で研鑽を積んでいます。初心者から師範級までいっせいに稽古していることになりますが、先生がそれぞれのレベルに合った課題をきめ細かに指導していますので、初心者から上級者まで、稽古で学ぶことができ、上級者からのアドバイスも容易に得られる環境です。
各支部道場には、目指すところは皆同じく「宗家の動き」であっても、アプローチの仕方がまったく違い、稽古に特徴があると聞きます。また、先生との相性もあります。最終的にはご自身が見学なさってどの支部に所属するか決められたらよろしいかと思います。
また、当道場はあまり上下関係が無く、また、社会人が多く、皆さん常識人として適切な距離をとって所属されているように見受けられます。どの道場に所属するにしても所属している人達との相性もありますので、見学をして雰囲気を確かめてください。